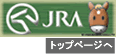
![]()
![]() 11⇒2、12、3⇔2、12、3、7、6 (18点)
11⇒2、12、3⇔2、12、3、7、6 (18点)
![]() 11、2、12、3、7
11、2、12、3、7
![]() 11⇔2、12、3、7
11⇔2、12、3、7
ヴィンセンシオには危うさしかない。とにかく並ぶ数字は眉唾ものばかり。その筆頭が前走のレコード勝ちに価値を見出せるかどうかだろう。同日の2歳新馬千二1分9秒0、古馬2勝千二で1分7秒5。翌日の2歳未勝利千六で1分33秒4。レコード確定の開幕週馬場で流れが速くなって当然のレコード更新をどう評価するか。
さらに最速上がりの3着馬より0秒8も遅かった上がり時計が決定的な格差、落差の象徴。少なくても一番中身の濃いレースだったのは唯一上がり33秒台だった3着リトルジャイアンツ(次走自己条件1着⇒共同通信杯3着)。同タイム2着ゲルチュタール(次走京成杯惨敗)とヴィンが同等と評価するのが常識で、本来は1分58秒台の持ち時計があれば重賞でも楽勝可能なはずのゲルチュが惨敗したことで疑念が確信に変わる。
過去の傾向から上がり33秒台以下を未経験が致命的な追い打ちになる。前々走は最速上がり33秒台以下が標準馬場で超スローを上がりNo3の35秒台。前走も2着馬より劣る上がりNo3は瞬発力勝負に課題を示すのが時間の問題となっている。
しかも最近の次走凡走傾向にある加速するレースラップだ。反動なのか、逆に前半のラップが厳しくないレースレベルに問題なのかは微妙だが、直後のレースでは各馬の苦戦続きが現実。残り4ハロンから加速した葉牡丹賞組の次走が3着馬以外の苦戦からも例外ではないことがうかがえる。
2戦2勝、レコードホルダー、超良血馬に名手配置。字面のいいブランド馬はすべての数字を打ち消すほど弱点を抱えていることが否めない。
ナグルファルにも死角が見え隠れしている。まずは上がり33秒台が未経験。前走は同日の未勝利より速いラップで時計が0秒6しか上回らなかったことにもレースレベルに懸念が生まれている。何より少頭数競馬から一気の多頭数。前々走で少し行きたがったことに加えて前走でもうひと回り以上の馬体成長に課題を示したことなど、少なくても前走の時点で心身両面の成長待ちだった。完成形よりかなり下の段階であることが示されている。しかも直線坂コースの未経験は過去の好走傾向に反している。
過去10年の3着以内の30頭中、直線坂コースが未経験だったのは16年1着のマカヒキだけ。そのマカヒキでも上がり33秒台以下がキャリア2戦の京都で2回。自身のベスト上がり時計32秒6を叩き出している。現時点ではマカヒキを物差しにすれば、大人と子供の差ぐらいの落差。マカヒキと同じような頭数経験で同じ2戦2回の最速上がり経験。二千の持ち時計はナグルがズバ抜けていいが、それでも頼りなさを感じるのは裏付けのない平凡な瞬発力からか。
いずれにしても2戦2勝馬、または3連勝以外の前2走で連勝中の馬は過大評価を受けやすい近年の流れ。20年サトノフラッグ、16年マカヒキ、リオンディーズ、15年サトノクラウンは3着以内だったものの、24年トロヴァトーレ、ダノンアエズロック、ファビラススター。22年インダストリア、ジャスティンロック。21年ワンデイモア。19年ラストドラフト。18年オブセッション。17年ダイワキャグニー。15年シャイニングレイ。これだけ馬券圏外になれぱ偶然というより必然。
負けた馬の特徴にそれまで先行脚質が多いことからもますますナグルの危うさが増していく。時計も上がりもごく標準レベルの2連勝に何の価値も驚きもなく、むしろキャリアを積んでも経験値はほぼ変わらない現状に嫌気が出る。厳しいレースを使って成長をつかむより賞金加算を選んだツケがここで出そう。