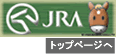
![]()
![]() 9⇔6、3、1、18⇒6、3、1、18、7 (32点)
9⇔6、3、1、18⇒6、3、1、18、7 (32点)
![]() 9⇔6、3、1、18、7
9⇔6、3、1、18、7
時代が変われば競馬はもちろん、ローテも変わる。90年までの主流は阪神4歳牝馬特別(千四)からのステップが王道だったが、91年アグネスフローラがチューリップ賞から桜花賞勝ちして潮目が完全に変わった。そこから5年連続で桜花賞馬がこのローテ。91年から24年まで前走チューリップ賞組が1着18回、2着17回、3着11回、4着11回、5着12回。34年間で5割以上の勝率はもはや"鉄板ローテ"そのものだったが、17年から桜花賞馬にチューリップ賞組はいなくなっているのが現実。近年の傾向はさらに変化があることをにおわせている。
ジュベナイルF、または朝日杯という年末からの直行組が猛威を振るい出してきた。14年2着レッドリヴェールからしばらく出走がなく、17年朝日杯から挑んだミスエルテの失敗で冒険する陣営がいなくなっていたが、19年朝日杯3着から桜花賞を勝ったグランアレグリアの成功でまたも陣営の意識が変わっただろう。その後の年末から直行ローテは
24年1着アスコリピチェーノ(ジュベナイル3人気1着)
2着ステレンボッシュ(ジュベナイルF5人気2着)。
23年1着リバティアイランド(ジュベナイルF1人気1着)
6着シンリョクカ(ジュベナイルF12人気2着)
11着ラヴェル(ジュベナイルF4人気11着)。
22年18着ラブリイユアアイズ(ジュベナイルF8人気2着)
21年1着ソダシ(ジュベナイルF1人気1着)
2着サトノレイナス(ジュベナイルF2人気2着)
20年10着リアアメリア(ジュベナイルF1人気4着)
ここ5年で3勝。人気と着順がしっかりリンクすれば桜花賞好走に直結するのが過去の傾向。今年も強力な2頭が挑んでくる。アルマヴェローチェ(ジュベナイルF5人気1着)、ブラウンラチェット(ジュベナイルF1人気16着)。中でもアルマの前走は強烈なインパクトを残している。
前日の古馬オープン特別と5ハロン通過が同タイムで、勝ち時計はわずか0秒5劣っただけ。古馬オープン特別の6着に相当する数字でクラシック直結レベルと確信させた。
前々走は直線で内から伸びを欠いていた当日傾向に反してラチ沿いから最速上がりに価値。前走は4角で前の馬の斜行によって急なコース変更を余儀なくされたが、残り250から2着馬ビップデイジーとの併せ馬に競り勝っている。千六適性の高さと瞬発力勝負の強さ。馬場不問のオールラウンダーにとって良馬場でも道悪でも同じようなパフォーマンスを確約できるのも強みだ。
今年のクイーンCがレースレコードだったが、同週の共同通信杯もレースレコードタイ。時計が出るのが当然の超高速馬場で相当な割り引きが必要になっていることは間違いない。
同週で行われたクイーンCと共同通信杯は25~19年の勝ち時計は
(1322・1460)(1331・1480)(稍1331・1470)(1341・稍1479)(1333・1476)(1340・稍1496)(1342・1468)。共同通信杯とともにレベルが高いか、ともに標準かのどちらかだが、同日の古馬1勝千六で1分33秒5を物差しにすればそれほど強調できる数字でもないことがうかがえる。さらにクイーンCからのステップ馬は
クイーンC着順 (桜花賞人気・着順)
24年1着クイーンズウォーク(3人8着)
23年1着ハーパー(3人4着) 2着ドゥアイズ(4人5着)
22年1着プレサージュリフト(4人11着)
2着スターズオンアース(7人1着)
3着ベルクレスタ(9人7着)
21年1着アカイトリノムスメ(4人4着) 2着アールドヴィーヴル(5人5着)
20年1着ミヤマザクラ(7人5着) 2着マジックキャッスル(8人12着)
成功例の絶対的な少なさからむしろクイーンCからのステップは"鬼門"に近い。ある程度の人気でも結果が出てないのが現実。例年より1~1秒5ほど速い馬場の今年も価値を見出せないだけにエンブロイダリーを主役としては扱えない。
少なくても時代に逆行したキャリアの多さ。過去10年の1~3着馬でキャリア5戦以上は30頭中わずか7頭。過去2年では1頭もいない。しかも早期デビュー(6月)だからこそ、牡馬も牝馬も十分な休養によってダメージ回復が必須条件だが、その傾向も無視したローテで疑念が生まれてくる。
過去10年で6月デビューの桜花賞3着以内は19年グランアレグリア(キャリア3戦、年明け初戦)、21年サトノレイナス(キャリア3戦、年明け初戦)、24年アスコリビチェーノ(キャリア3戦、年明け初戦)。これを7月デビューまで広げても17年ソウルスターリング(キャリア4戦、年明け2戦目)、20年スマイルカナ(キャリア5戦、年明け3戦目)。21年ソダシ(キャリア4戦、年明け初戦)。23年リバティアイランド(キャリア3戦、年明け初戦)。24年ステレンボッシュ(キャリア4戦、年明け初戦)。
7月デビューのスマイルだけは特例だが、その他はキャリア4戦以内で年明け初戦が王道になっている。すでに6、7月でも大敵の暑さにやられる馬が多数存在する近年の競馬から一番の回復は十分な休養であることは間違いない。
エンブロは馬場を差し引いても前走で走りすぎたことが大きな誤算。さらに関西へ初遠征が追い打ちか。初遠征でも結果を出した過去の例はわずか。持ち時計を含めた数字と鞍上だけが頼りで人気でも凄みを感じない。
ビッブデイジーの前走は鞍上不安がそのまま的中した。逃げ馬の直後、ラチ沿いで引っ掛かって折り合いを欠いたからこそ、4角で勝ち馬より脚色は上回っていたが最後まで交わせなかったか。いずれにしても鞍上はGⅠどころか、最近はGⅡも勝てなくなった落ち目ぶり。21年をピークにしてすでにV字回復は絶望的な年齢になっていることを忘れてはならない。大事なレースでのポカはこれまでもこれからも避けられないロートル感が足を引っ張ることを考慮しての狙いでいいだろう。そもそも名手ならば先を見据えた立ち回りをするのが常識だが、この馬はその場しのぎで極端すぎる乗り方を連発。本番の立ち回りをますます難しくさせて本番でどのような立ち回りになるのか、鞍上自ら窮地に追い込んでいる。前々走は馬群をうまく捌いたロスのない立ち回り。ほぼフロック駆けに近い奇跡の立ち回りは大一番で再現できる確率としては極めて低い。
エンブロ同様に前走でレースレコードを叩き出したエリカエクスプレスの取捨も難しい。何より良績なしのフェアリーSからのステップ。しかもキャリアはわずか2戦だけ。できるだけダメージを少なくするのが近年のクラシック路線とはいえ、道中はハナか、ラチ沿いの位置取りから直線の追い比べ。全力で追い合う相手がいないほど楽勝で激しくモマれたことのない経験値の低さがどうにも引っ掛かる。現実に前走は前々走のスムーズな立ち回りから一変。直線を待たずして惨敗もあり得たほどの折り合い難となったことがすべてを物語るだろう。好枠を引いたことによって位置取りはハナか、2番手か、逃げ馬の直後かの三択。同型同士のつぶし合いにならないことを祈るだけ。
ショウナンザナドゥが前走でV字回復には正直驚いたが、千六より千四がベターだったことが裏付けられたことに変わりない。デビュー当初の千六は素質と勢いだけでこなしてきた典型的な例だろう。現実に走るたびに千六ではトーンダウン。デビュー2戦で連続の最速上がりが、4走前から前々走まで上がりNo3、9、8。前走で再び最速上がりに返り咲いたことが距離適性の落差を示している。さらに付け加えれば千四のトライアル戦からの桜花賞への好走パターンはひと昔前、昭和時代の黄金ローテ。手薄なメンバーで勝っても何の価値を見出せないのが現代競馬の象徴的な変化となっている。前走で馬体はギリギリ。
ショウナンの前走千四からのステップが古さを感じさせる距離延長ローテならば、距離短縮ローテはすでに過去の遺物だろう。過去10年の3着以内に前走千八以上は皆無。リンクスティップには最凶レベルのジンクスを打ち破るほどの数字を兼ね備えてない。確かにメンバー比較ではここで主役級になっても驚かない。前走の勝ち馬は東スポ杯2着サトノシャイニング、3着ランスオブカオスは次走のチャーチルDCで重賞馬となった。1、3着馬がこの春のGⅠ路線でもある程度の人気を集めるほどだが、上がり33秒台以下の未経験は近年の桜花賞好走馬とは相反する異質な存在。千四からのステップも含めてこの10年の桜花賞3着以内の馬で千六未経験馬はゼロ。常識的にはオークス照準とみるべき。
本来、もっと重賞を勝てる計算ができた馬にもかかわらず、短いピークで終わるのがブラウンラチェットの厩舎の特徴。近年でもソールオリエンス(皐月賞勝ちからスランプ)、シュネルマイスター(GⅠで2着2回の実績を挟みながら毎日王冠勝ち後から次の勝ち鞍まで1年半の月日)、ユーバーレーベン(オークス勝ち後は8戦して3回の二桁着順もあって未連対)。ウインマリリンは年をまたいで重賞を勝ったがアサマノイタズラ、マルターズディオサは重賞勝ちを境に燃え尽きている。
まさに厩舎のイメージどおりの戦績になりつつあるのがブラウンだ。そもそも前走は木曜検量の時点で大幅な馬体減が避けられない数字が出ていただけに出走回避の英断が必要だった。当日の見た目にそれほどの細さは感じなくても、この結果が状態の悪さを示していたことは明らかだろう。いずれにしても外厩か、美浦かのどちらかで"仕上げの失敗"。仮に美浦での失敗ならば、過去の傾向からもすでに"燃え尽き症候群"の段階に入った可能性は極めて高くなる。大惨敗にもかかわらず、年末からの直行ローテを早々に選択したことも不可解そのもの。近年の好走ローテとはいえ、フィジカルの回復は可能でもメンタルの完全復活はさすがに望めないか。ひたすら外差しの極悪馬場になることを待つしかない。