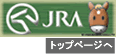
![]()
![]() 5⇒12⇔8、13、14、6、9、3 (12点)
5⇒12⇔8、13、14、6、9、3 (12点)
5⇒8、13⇔8、13、14、6、9 (14点)
時代錯誤のマラソンレースでたとえ勝っても種牡馬としての価値が極端に上がることはないが、サンライズアースは確実に名馬へと近づいている。まさに別馬のような成長力。すべてにおいて昨年、春のクラシック時とはレベルもスケールもすべてが変わってきた。兄が交流重賞ホルダーらしく、切れ不足とスピード不足は数字的にも明確に表れていたが、晩成型のステイヤーとして頂点にたどり着くことが時間の問題とにおわせるほど勢いづいている。何より瞬発力の変化と強化。良くて上がり34秒台で皐月賞、ダービー、日経新春杯はそれぞれ上がりNo11、15、16。ペース無視の下手な立ち回りだったことを割り引いても、先々の見通しがまったく立たなかった状況の中からV字の成長曲線は驚きしかない。前々走で上がりNo4はもちろん、何より前走の最速上がりは上がりNo3より0秒5、No4より1秒も速い数字に凄みを感じさせる。馬場差的な計算から3分3秒台ほどの価値を見出せないとはいえ、残り5ハロンから11秒台突入という過酷なラップを圧勝したことはメンバーレベルの低下が避けられない天皇賞春ではこれだけで主役として扱えるだろう。常識的なラップで立ち回れるかどうかだけ。名手ならつかまっているだけで勝てるほど能力は抜けている。
ジャスティンパレスが勝てるGⅠはこの天皇賞春しかなくなった。すでに瞬発力に限界を示している6歳馬。ひたすら直線まで脚をためてようやく上位の上がり時計を爆発させるのが特徴にもかかわらず、鞍上が馬の特性を理解しないままでコンビ続投ではもう策がなくなったも同然。GⅠ未勝利の鞍上に託せばそれだけリスクがあることの象徴的な事例になっている。23年宝塚記念は上がりNo3、23年天皇賞秋は上がりNo1、23年有馬記念は上がりNo2。5走前は道悪で不発に終わったことで度外視できても、4走前の上がりNo2、3走前の上がりNo3で前々走の上がりNo4。これだけ上位に匹敵する鋭さを兼ね備えているはずが、前走の上がりNo7ですべてが崩れ去ったか。休み明け(310204)の仕上がり早にもかかわらず、4角前の手応えの悪さは惨敗も頭によぎるほど最悪な行きっぷり。少なくても前々走までのコンビより相性の悪さが否めなくなったことは間違いない。2年前の天皇賞春勝ちは稍重と名手配置。1度下り坂に入ると回復の望めめないディープ産駒が23年秋から連対実績なしがすべてを物語る。
重賞勝ちはGⅢの1勝だけ。しかも良績のないダイヤモンドSからのステップ。名手配置だけで売れているようなヘデントールは本当に強いのか。数々の数字を紐解いても確たる裏付けが浮かんでこないのが現実だ。
過去10年の天皇賞春3着以内でダイヤモンドSから直行だったのは
22年3着テーオーロイヤル(1着3301、上がりNo4。重賞勝ちはこれだけ二千四以上は6戦目)
15年2着フェイムゲーム(1着3319、最速上がり。ダイヤモンドS2勝、アルゼンチン共和国杯勝ちを含めた重賞4勝。ダイヤモンドS1勝のみで二千四以上1戦だけの経験だった前年は天皇賞春6着だった)
58キロは未経験、三千の持ち時計はNo9。前走の2着馬は12人気で古馬重賞で掲示板の経験もなし。3着馬は10人気で重賞初出走馬。この程度の相手にぶっち切り勝ちは当然の結果。むしろハンデ57キロという恵まれすぎた斤量で走れたことが勝利に直結したと割り切るべき。菊花賞とダイヤモンドSは平凡な勝ち時計で微妙なレベルだけに勝っても惨敗しても驚くことはない。ただただこの数カ月での成長力に期待するしかない。
ビザンチンドリームは前走だけで評価できない。結果的に残り1ハロンを残して勝負が決まったような完勝でもどこか微妙な中身だったことが否めない。道中は各馬が超折り合い難の中でスムーズな立ち回りがひとつの勝因。直線を待たずして脱落した馬も2、3頭いて、直線の追い比べでは他馬がすでにギブアップ状態に近かったために一瞬にして先頭に立てたか。いずれにしてもいい脚一瞬だけで最後詰め寄られて、この馬は直線の短いコースが合うことが証明されたレースでもあった。今まで時計と瞬発力を同時に求められたレースではことごとく惨敗になった過去の姿と大きな成長がない可能性。混戦が大前提になる。
ショウナンラプンタの前走は正直、人馬ともにがっかり。結局、今まで失敗してきたレースと同じ乗り方に終始したのは驚きしかなかった。しかも道中ははるか後方で折り合い難。鞍上から刺激期待だったが、むしろ鞍上弱化の結果で前々走までの評価以上に低空飛行が避けられなくなっただろう。大一番を見据えて脚を測るための完全試走なのか、前々走の最速上がりでためれば切れると思い込んだか。いずれにもこの鞍上でもすでに矯正不可能な悪癖馬ならば、はまってワイドラインの走りが限界。行きたがっていた菊花賞で距離の限界も感じさせただけにかなり大胆な騎乗方法が求められる。次の新鮮味ある乗り替わりまで主役としての扱いはお預け。