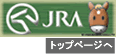
![]()
![]() 9⇒4、12、3、5 (36点) 4⇒12、3、5 (18点)
9⇒4、12、3、5 (36点) 4⇒12、3、5 (18点)
![]() 3-4、12、5-
3-4、12、5-
9、4、12、5、6、15、16、10、14 (21点)
![]() 4、12、3、5、6⇒9 9、4、12、5、6⇒3 4⇒12、5
4、12、3、5、6⇒9 9、4、12、5、6⇒3 4⇒12、5
先週の七夕賞が象徴的。前走が古馬3勝で水準並みの時計でも十分に太刀打ちできることが証明された。水準以上ならば堂々の主役として扱えるのが今のGⅢレベルに異論はないだろう。馬の層の薄さと重賞の乱立。ここのメンバーは前走が重賞以外か、重賞の二桁着順という馬が合わせて13頭もいれば必然的に格下からの挑戦でも勝ち負け可能ということ。さらなるレベル低下をにおわせる追い打ちは前走で上がり33秒台以下がゼロ。現代競馬ではまさに信じられないほど低調なメンバーが揃ったことが決定づけられている。
それでもメリオーレムを全幅の信頼を置けないのが現実。少なくてもここで勝ち負け可能な数字を兼ね備えてない。もとより瞬発力不足でオープン入りに手間取った過去。前走で突然瞬発力勝負に強くなることはなく、むしろこれまでもこれからも同じような惜敗続きが常識的な見解だろう。最速上がりは1年以上も未経験。前日の古馬1勝で1分58秒3という超高速馬場だった前々走を除けば、二千は1分59秒台がこの馬の標準スピード。時計も上がりも極限レベルにならないとはいえ、古馬重賞初挑戦の馬が持ち時計No6、二千限定のベスト上がり時計No4程度の数字には物足りなさを感じる。時計と瞬発力を同時に求められない流れで台頭か。
レコード決着の3着となったマイネルメモリーも評価を上げられない。JRAが今までの馬場と変えたのは意図的なのか、失敗したのかはわからないが今年の函館は京都並みの超高速馬場に変貌した。その後もレコード連発で"洋芝=時計がかかる"という常識を根底から覆したことは間違いなく、馬場差比較で割り引くと今年の時計は低調なレベルという評価に落ち着く。どのみち前走のように置かれすぎて勝負どころからマクり始めて4角ブン回し。前走は7、8ハロン目が12秒台だったからマクれただけで、今回確実に11秒台突入するラップで真価を問うべき。いずれにしてもはまってワイドラインが限界。
シェイクマイハートは鞍上に嫌気。これぞ重賞無縁の鞍上の象徴的なへぐりで先週の重賞も取り逃がしている。ハナを切れるかどうかの戦前の予想を軽く裏切る最悪騎乗ぶり。同型逃げ馬に簡単にハナを譲って自分は早々に折り合い専念。瞬発力勝負にまったく良績なしにもかかわらず、スローの流れを末脚頼りに徹するという不可解そのものだったのが先週の重賞レースの内容だった。レースを読めないのか、ペースを読めないのか。どちらにしても気楽に乗れる先行馬しか勝ち負けの計算できない鞍上配置のままでは取りこぼし前提の狙い。持ち時計No8、二千限定のベスト上がり時計No14。明らかに瞬発力不足を示す数字があるにもかかわらず、ここでも差し競馬にこだわるのが鞍上の性格として受け止めるしかない。必要以上に控えた時点で勝ち負けから遠ざかる。
デビュー6着以来、千八を使わず、ダートにも挑戦せず、ブリンカーも試さずでセン馬へ。安易な英断だったと言わざるを得ないのがリカンカブールだろう。デビューから瞬発力型として完成されていた馬を中山金杯快勝後は一変した先行策がことごとく裏目。それでも4走前は2着に0秒5差、3走前は3着、前走は1~3着馬より2キロ増、4着馬より3キロ増の斤量で3着に0秒7差ならば乗り方ひとつ、マネジメントひとつで変わる余地を残していた重賞ホルダーということ。前走の惨敗がよほど頭にきたのか、セン馬になって今更条件変更、路線変更というある意味、悪手の英断だけに、ここでの結果が即現役生活の長さに直結することは言うまでもない。休み明け(411104)と平坦(200011)と新鮮味ある乗り替わりで変わる条件、刺激ある条件で少なくてもきっかけをつかみたい。