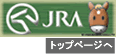
![]()
![]() 2、17、16、1⇒
2、17、16、1⇒
2、17、16、1、11、9⇒2、17、16、1、11、9 (80点)
先週の安田記念も近年稀にみる低レベル。同日1勝クラスよりわずか0秒8上回っただけの平凡な勝ち時計で一気に興ざめのGⅠとなった。そもそも5ハロン通過で0秒2だけ速かったペースも不可解そのもの。今年も1分31秒台以下が標準レベルの高速馬場ではあり得ない流れの遅さだった。上がり時計が大幅に上回れば納得できるが、上がり時計は0秒6上回っただけ。低レベルの決定的な数字だったのがわずか0秒2しか上回らなかった最速上がり。だからこそ、前々で捌いたジャンタルマンタルが勝てたということ。平凡な勝ち時計に加えて上がり34秒台で振り切れる展開の利とメンバーに恵まれたことはいいわけ無用の低調さとして割り切るしかなかった。
これまでマイル以下で顕著に表れていたこれらの傾向だったが、どうやら主流のGⅠでも随所に表れ出したことが否めない。まさに昨年の有馬記念は象徴的。同日の古馬2勝より5ハロン通過で0秒8遅く、勝ち時計はわずか0秒4上回った程度。ラスト5ハロン有馬が57秒9、古馬2勝が59秒4に圧倒的なレベル差がうかがえるが、そでもここまで勝ち時計のレベルが下げれば、持ち時計や過去の実績などほぼ関係なしになったことは間違いない。いかに中団より前々で立ち回れて、どれだけの瞬発力が使えるかということだけ。それがここ宝塚記念でも共通項になっただろう。
24年有馬記念
(勝ち時計-前半5ハロン=最速上がり[ラスト5ハロンのレースラップ])
2318(629-352=349[113-114-116-115-121])
24年有馬記念同日の古馬2勝
2322(621-364=355[115-115-120-119-125])
1秒2差の上がり差で何とかオープン特別程度のレベルを示せたが、最速上がりのレガレイラは9着馬と上がり同タイム。上がり0秒3差以内に6頭。その中で不利な枠順でもなく、中団でスムーズに立ち回れたのが結果的に勝ち馬だったということ。とにかく絶対的に前々有利だった有馬記念は逃げ先行馬より中団より後方から上位になった馬の中身が濃いことが明白となっている。
24年有馬記念も今年の大阪杯もレース展開的には似ている。どちらもラスト5ハロンから一気にペースが上がって持続型の瞬発力を求められた。
ラスト5ハロンのレースラップ
有馬記念
113-114-116-115-121
大阪杯
117-119-120-114-117
宝塚記念(ラスト5ハロンのレースラップ。1~3着馬の上がり時計と上がりランキング)
京都24年重
122-114-117-113-115。最速上がりは1着と2着の340、NO4は3着の348
23年良
125-119-117-120-118。最速は2着の346、NO2は1着の348、NO3は3着の351
22年良
119-118-119-120-124。最速は2着の359、NO2は3着の360、NO3は1着の361
21年良
123-115-115-115-117。最速は1着の344、NO4は3着の350、NO5は2着の351
20年稍
124-124-119-121-123。最速は1着の363、NO2は2着の372、NO4は3着の376
19年良
120-116-115-114-124。最速は1着の352、NO2は3着の357、NO3は2着の358
まさに宝塚記念の最重要数値は上がり時計となっていることの証。昨年の京都を度外視してもしなくても1着馬は上がりNo1~3以内で、とりわけ最速上がりの馬が勝ち上がっている確率が多い。2、3着馬は上がりNo5以内でほぼNo3以内で決まっている傾向の強さから一過性でないことがうかがえる。1~3着馬は前3走以内で最速上がりか、上がり33秒台以下を叩き出した馬に限られていることも付け加えたい。
過去10年の傾向から紐解くと19~21年ごろから様変わりしてきたか。上がり時計重視が近年の傾向で、21年から3着以内の12頭すべてが前3走以内で最速上がりか、上がり33秒台以下の経験があった。3走前に上がり33秒台で一応クリアしているとはいえ、ここ5戦で上がりNo5以内がなく、持ち時計No14のベラジオオペラが時計と上がりだけでここ通用の裏付けなしは明らか。直線の内外で馬場差が出れば最内枠がアダとなる可能性も秘めている。とにかく器用さだけが頼り。まずは馬場の回復具合によって扱いの取捨、強弱を決めるべき。
そのベラジオオペラにとって強調点は2つしかない。コースと恵みの雨。まさに阪神(400000)で数字に表れるスペシャリスト。勝ったレースが新馬、チャレンジC、大阪杯2勝。4勝中3勝が重賞だから恐れ入る。しかも3戦の二千ですべて1分58秒台。走るたびに時計短縮していることからも阪神二千では無敵としての扱いも可能なほどの強さを誇っている。
新馬勝ちの稍重(100000)、皐月賞10着以外はスプリングS1着と大阪杯3着の重(101001)で時計と瞬発力を同時に求められた際の結果が皆無の馬にとって少なくてもパンパンの良馬場より条件がいい。
最近のGⅠ傾向は驚くほど時計の遅いレースか、上がりのかかるレースか、瞬発力不足を補える条件になるかどうか。単純に瞬発力だけを求められる条件となると有馬記念の悪夢がよみがえるが、ハイペースで後続馬にはなし崩しに脚を使わせる展開が唯一の勝ちパターンとなる。
レガレイラはグランプリホースという威厳など微塵もない。前走は平凡な時計と上がりで理想的な枠順と位置取りがすべての勝因だったと割り切るべきだろう。5ハロン通過が過去10年でブービーとなる遅いラップ。5ハロン通過がワーストとなった14年も牝馬、ジェンティルドンナが終始2、3番手の立ち回りで後続を完封して引退している。
とにかく数字的な強みはゼロと断言できるほど低調な数字が並ぶ。持ち時計二千二、二千四、二千、千八はそれぞれNo9、9、9、11。二千二限定のベスト上がり時計No6。阪神未経験に加えて京都、中京未勝利で長距離輸送そのものに実績がないことにさらなる危うさが加わってくる。
古馬重賞未勝利馬が海外競馬に魅了されて奈落の底へ落ちかけているのがドゥレッツァだろう。海外でも時計勝負が生命線になる日本馬が、わざわざ時計のかかるイギリスに挑戦するなど本来ならば言語道断の最悪マネジメント。まさにクラブ馬だけに許される海外遠征だった。前走も着差以上の完敗。最速上がりを連発していた3歳までのイメージとは異なり、一瞬の脚で終わった内容からも距離が合わぬか、前々が合わぬかのどちらかの条件で足を引っ張っていることは間違いない。
いずれにしても菊花賞の好時計は馬場がすべて。この馬は二千前後がベストというイメージがますます強まれば、JRAでは久しぶりの二千四より短いレースに活路を見出せる可能性は高まっている。勝ちにこだわる乗り方ならば徹底待機、大きく崩れない安全策ならばここも前々勝負。鞍上の選択に注目。
ショウナンラプンタは前走が2回目のコンビとなったが、それでも馬の特徴を理解できずの立ち回りだった。もとより仕掛けの難しい癖馬に完成されたとはいえ、いい脚が一瞬で終わることは周知のとおり。3角前まで勝ち馬より後方にもかかわらず、4角で勝ち馬より前方だった位置取りがすべてを物語っている。残り1ハロン付近で先頭に立ったが同時にまとめて外から2頭に交わされた内容は悲観することなく、むしろ仕掛けひとつでGⅠ制覇が計算できることを証明した。この馬がステイヤーなど1度もイメージしたことがなく、ここ2戦のマクり失敗が中距離戦への布石となることを確信している。頼りない鞍上でも近走より気楽に乗れる立場が何よりの好材料。腹をくくって直線勝負こそが一番好走の近道となることを鞍上が理解しているかどうかがすべてのカギを握る。
現役最高レベルの道悪巧者、ソールオリエンスは今や道悪のみが好走条件となっている。良馬場では完全なる格下扱いでも、少しでも馬場が渋れば逞しさと凄みを増して一気に主役へ踊り出る変身ぶり。それがGⅠであってもなくても関係なしに好走を続けていることは偶然ではなく、必然的な結果であることも証明されている。とにかく重よりさらなる馬場悪化ならば、不動の中心馬へ格上げがセオリーとなるぐらい信頼度は高い。
重の皐月賞1着、極悪馬場の宝塚記念2着。とりわけ昨年の宝塚記念は各馬が外ラチまでコース変更するほど馬場が荒れていた中で、上がりNo3より0秒6も速かったという勝ち馬と同タイムの最速上がりに絶大なる価値と信頼を置ける。時計を求められた時点で圏外となることはこれまでもこれからも変わらずだが、前2走でいずれも最速上がりだったのはこのメンバーでこの馬だけという事実を忘れてはならない。